1.最古の具注暦 奈良県石神遺跡出土具注暦木簡
2002年に発掘され、2003年春に発表された木板に書かれた具中暦。これが和暦の開発動機でもありました。
年代同定の手順はまず発見された具注暦から特定できそうな語句を拾い検索にかけます。 表面から始めると適当な検索語句は以下です。
1)辛酉 破 上弦 (上弦は月が上弦の日、旧暦7日頃)
2)壬戌 破 三月節 (三月節は節気が「清明」の日)
これらをキーワードにして1) 2)別々に和暦検索で検索し、エクセルで結果を合わせてユリウス日で日付順にソートしたものが以下です。
表面の結果
この中で1)及び2)の条件で検索した結果の日付が連続しているのは持統天皇3年3月(689年)と延徳2年3月(1490年)の2年。したがってこの2年が候補となります。
次に裏面に行くと適当な検索語句は以下です。
1)戊戌 執 望 (望は月が満月日、旧暦15日頃)
2)己亥 破 往亡 (往亡は暦注の一つ、節からの日付で決まる)
表と同じく、これらをキーワードにして1) 2)別々に和暦検索で検索し、エクセルで結果を合わせてユリウス日で日付順にソートしたものが以下です。
裏面の結果
この中で1)及び2)の条件で日付が連続しているのは持統天皇3年4月(689年)のみです。
また、表面と裏面は同年代の暦と推定されるので、結論として表面は持統天皇3年3月(689年)、裏面は同4月の暦と同定できます。
<参考文献> 奈良文化財研究所 紀要(2003) II-3 飛鳥地域等の調査
(2007/09/21 記載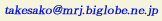 ) )
|
|