|
「具注暦/仮名暦」は古い時代の日本の暦/暦注情報を提供するWEBサービスです。 「具注暦/仮名暦」は「和暦(わごよみ)」の計算結果を使い1684年までは具注暦形式で、1685年から1872年までは仮名暦で表示しています。 対応年は日本書紀に記載されている最初の年(神武天皇即位前-666年)より太陽暦に改暦される明治5年(1872年)までを対象とします。 1. 具注暦の説明(-666年〜1684年) 1)使用した暦法と適用年代 「具注暦(ぐちゅうれき)」は「和暦(わごよみ)」同様以下の暦法にもとづいています。 (0)儀鳳暦 (平朔弦望):-666年から444年 (1)元嘉暦 (平朔弦望):445年から696年 (2)儀鳳暦 (定朔弦望):697年から763年 (望弦が日出小余に満たない場合一日後退) (3)大衍暦 (定朔弦望):764年から861年 (望弦が日出小余に満たない場合一日後退) (4)宣明暦 (定朔弦望):862年から1684年 (望弦は昏明小余に満たない場合一日後退) 望弦は「御堂関白記」中261回の記載に対し14回が計算と会わず。 殆どが昏明小余に満たない場合でも一日後退していないケース。 意図的なものか計算方法の違いかはいまのところ不明。 2)暦注情報 参考文献にあげる資料を参考に具注暦下段(大歳/小歳/凶会/天恩/母倉/月徳/月徳合/復/重/九坎/厭對/歸忌/血忌/往亡/厭/無翹/天赦/歳徳/歳徳合/月殺)を表示しています。 「御堂関白記」「猪隈関白日記」で検証し、大歳小歳凶会を修正しました。(2007年1月14日) 大歳小歳凶会の配当 3)雑注情報(2007/ 2/18追加) 「御堂関白記」に記載の雑注をベースに雑注情報を追加しました。「御堂関白記」に記載無い日付は京都大学及び国立天文台蔵「大唐陰陽書」の内容を参考にしました。(主に京都大学蔵版を使用。)この場合雑注の最後に「*」マークをつけています。 ただし、「御堂関白記」の中でも記載内容に違いがあり、時代が下がるに従い削られていくので絶対的なものではありません。AD1000年頃の内容として参考にしてください。特に元嘉暦以前については意味が無いとは思いますが現時点ではあえて削りません。 雑注は計算上日蝕/月蝕の予想される日には記載されませんが現時点では日蝕/月蝕に拘らず記載しています。 2. 仮名暦の説明(1685年〜1872年) 1)使用した暦法と適用年代 仮名暦は「和暦(わごよみ)」後半と同じく各年代につき以下の暦法で計算しています。 (5)貞享暦 (定朔):1685年〜1754年 (6)宝暦暦 (定朔):1755年〜1770年 (7)修正宝暦暦 (定朔):1771年〜1797年 (8)寛政暦 (定朔):1798年〜1843年 (9)天保暦 (定朔):1844年〜1872年 2)暦注情報 参考文献にあげる資料を参考に仮名暦中段(節分/彼岸/杜日/八十八夜/入梅/土用/二百十日/八専/十方暮/天一天上/三伏)及び下段(受死日●/十死日/五墓日/帰忌日/血忌日/重日/復日/天火日/地火日/大禍日/狼藉日/滅門日/凶会日/往亡日/天赦日/神吉日/大明日/鬼宿日/天恩日/母倉日/月徳日)を表示しています。 暦注は暦法/時代による変遷もありますので、実際に施行された暦と完全に一致しているわけではありません。「具注暦/仮名暦」は参考として使用ください。 3. 太陽暦施行以降(1872年〜2100年) 1)使用した暦法と適用年代 「和暦(わごよみ)」後半と同じく各年代につき以下の暦法で計算しています。 (10)天保暦 (定朔):1844年〜2100年 2)暦注情報 仮名暦に加え、六曜、九星及び戦後の「国民の祝日」を主に追加しました。 九星については流派があるようですが、一般的な方法で計算しています。 九星の閏については以下の年に置いています。 1882冬至 1894夏至 1905冬至 1916冬至 1928夏至 1939冬至 1951夏至 1962冬至 1974夏至 1985冬至 1997夏至 2008冬至 2019冬至 2031冬至 2042冬至 2054夏至 2065冬至 2077夏至 2088冬至 2100夏至 閏の置き方により前後の時期には違いがでますので注意ください。 「国民の祝日」は現時点(2008年8月)の法律による結果です。 4.西暦の表示 「具注暦(ぐちゅうれき)」は「和暦(わごよみ)」同様1582年10月4日までユリウス暦、翌日の10月15日以降をグレゴリオ暦により表示します。したがい1582年10月4日の翌日は10月15日となります。 また、,紀元前の年号については以下の方式でマイナス表示しています。 紀元1年(AD1年) : 1年 紀元前1年(BC1年) : 0年 紀元前2年(BC2年) : -1年 紀元前100年(BC100年) : -99年 5.入力方法 メニュー方式により1)元号(天皇紀年を含む)年代順、2)元号読方順、3)年代直接入力が選べます。また年代直接入力の場合は紀元前の用途は低いと考え紀元0年(BC1年)から1684年までの選択としました。元号で入力の場合年数のチェックはしていませんので結果として先の元号の年代へ移っている場合があります。 例えば入力:皇極天皇10年(実在せず)→出力:白雉 2年 6.著作権並びに注意事項等 「具注暦/仮名暦」並びに「和暦(わごよみ)」にて提供される情報、その他のデータ類の著作権は「和暦(わごよみ)」またはその引用元著作権者に帰属します。また、そのすべてについて「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き転載/2次利用はお断りします。 「具注暦/仮名暦」並びに「和暦(わごよみ)」の掲載内容の利用にあたっては自己の責任と判断のもとにご利用いただくものとし、万が一これらで提供される情報を利用されたことによっていかなる損害が生じても責任を負いません。 7.参考文献 「具注暦」関係 1)古川 麒一郎、伊東 和彦、 岡田 芳朗、 大谷 光男著 「日本暦日総覧〈具注暦篇 〉」 2)『ほき内伝』(中村 璋八著「日本陰陽道書の研究 」(1985)) 3)『長暦』(年代学研究会編「天文・暦・陰陽道」(1995)) 4)広瀬秀雄著「暦」(日本史小百科、1993) 5)内田正男著「暦と時の事典」(1986) 6)湯浅吉美編「日本暦日便覧」(1988) 7)大谷光男著「日本古代の徳具注暦と大唐陰陽書」(東洋学研究所集刊第22集,1991) 8)大谷光男著「麟徳具注暦(正倉院)と宣明具注暦」(東洋学研究所集刊第31集,2001) 9)岡田芳郎著「日本最古の暦」(歴史研究2003年4月号第503号) 10)陽明叢書「御堂関白記」(思文閣出版,1983) 11)大日本古記録「猪隈関白日記」(1983) 12)国会図書館蔵 安藤有益著「長慶宣明暦算法」寛文3年(1663) 13)京都大学蔵(電子公開版)「宣明暦」 14)京都大学蔵(電子公開版)「大唐陰陽書」(1-6月欠、その他ページ抜けあり。) 15)国立天文台蔵「大唐陰陽書」 「仮名暦」関係 1)内田正男著「暦と時の事典」(1986) 2)暦の会編「暦の百科事典」(1986) 3)仮名暦 -宝暦6年/寛政10年/天保15年(佐藤正次編「暦学史大全」1977) -貞享4年(国会図書館蔵)(マイクロYD-古-1239) -嘉永6年(暦の会編「暦の百科事典」) -安永8年/寛政11年/文化元年/文化11年/文化12年/文政10年/弘化元年/他 「現代の暦日」関係 1)西澤宥綜著「暦日大鑑」(1994) 2)日外アソシエーツ編「21世紀暦」(2000) 3)日外アソシエーツ編「20世紀暦」(1998) 8)変更履歴 (1)2006/12/19 WEB公開。 (2)2006/12/26 「歳徳、歳徳合、月殺」を追加。 (3)2007/ 1/14 大歳小歳凶会を修正。 (4)2007/ 1/28 上弦/望/下弦を追加。 (5)2007/ 2/18 雑注を追加。 (5)2007/ 2/25 七十二候/六十卦/土用/伐/天間/除手足甲/沐浴/五墓/六蛇七鳥八龍九虎を追加。 (6)2007/ 9/23 月建/日付/暦注による検索サービスを開始。(AD400年〜1684年迄) (7)2008/ 2/11 仮名暦サービスを開始。(AD1685年〜1872年迄) (8)2008/ 3/30 1070年の暦日を修正 (9)2008/ 8/24 2100年まで暦日を追加 (10)2011/ 4/ 2 ・「和暦」の計算を変更。(主に大衍暦の進朔) ・大衍暦以前の大歳小歳表示を変更 ・弦の計算に月/太陽の影響を考慮。後退を考慮。 ・神吉の選日を修正 (11)2015/ 3/13 ・「和暦」の変更に伴う変更。(五紀暦を大衍暦へ変更等) ・バージョン番号(v.20150313)の挿入。 (12)2015/ 8/ 7 ・儀鳳暦(697〜763)において「雨水」と「啓蟄」の節気の順番を変更。 (13)2016/10/11 ・不具合修正(垂仁天皇 29年(西暦0年)) (14)2019/ 1/ 8 ・不具合修正(11月付近の12直で「閉」を「平」としていた。) ・休日修正(山の日を追加。/即位関連) ・平成31年から新年号表示に変更(年内の変更は仕様でできない) (15)2019年 4月 1日 新元号「令和」を追加。 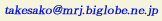
|