�@��������{�̗l�Ȓ��ܓx�Ȗk�̒n��œ��H�������ł���m���́A���H�H�r���̌��̉��܂����z�̉��܂��k�ɂ���ꍇ�̕�����ɂ���ꍇ��舳�|�I�ɑ傫���B���̐�����p�������H�\����@���ȕւׂ̈����ł͗z��@�ƌĂԁB���̗z��@�͒������@�̎���ɔ������ꗘ�p���ꂽ�B�z��@�͓��{�ɂ��V�P��Ɣ��ɓ`�d������{�̓��H�\��ɂ��g��ꂽ�B
�P�D���H�v�Z�ɂ����H�����m���̈Ⴂ�̌���
�P�D�P�@����̓��H�v�Z�@�ɂ�錟��
�@����̓��H�v�Z�ł͂܂����H���Ƀx�b�Z���v�f�����Ƃ߂���ɂ��ϑ��n�_�ɂ�������H�̏��v�Z����̂��ʏ�ł���B�M�҂̍쐬�������H�v�Z�v���O����Emapwin�ł͑��z�y�ь��̋O����JPL�̓V�̗�DE406�ŋ��߃x�b�Z���v�f���v�Z���Ă���B���̃x�b�Z���v�f�̒��Ƀ��Ƃ���p�����[�^1)������A����̓x�b�Z����ʂɓ��e���ꂽ���z�̒��S�ƌ��̒��S�Ƃ̍ŏ������̒l�ł���B���̃p�����[�^�̕������v���X�̎��ɂ́A���̒��S�����z�̒��S���k��ʂ������ƂɂȂ�A�t�̏ꍇ�͓�ł���B
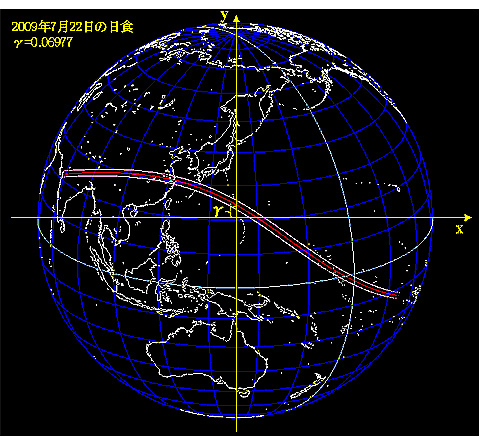
��������
1001�N����1200�N�܂ł�200�N�Ԃ̓��H�����s�Ŋϑ��������̗���ȉ��Ɏ����B
�\�|�P�@������H�v�Z�@�ł̋��s�ł̎����\��(����1001�N����1200�N)
|
���̈ʒu
|
�S���H��
|
���s�ł̎����\��
|
|
���z���k(����+�̏ꍇ)
|
249
|
72
|
|
���z����(����-�̏ꍇ)
|
242
|
8
|
|
���v
|
491
|
80
|
�@�@��-1�F�����\�̌v�Z��Emapwin�ɂ��B
�]���āA���H���Ɍ������z�̖k�ɂ���ꍇ�͓�ɂ���ꍇ���9�{�����s�Ō�����m��(72/80=90%)���������ƂɂȂ�B�܂���ɂȂ�ꍇ�ł����s�Ō�������H�͎��̂W��ł���A�@1047/3/29,�A1054/5/10,�B1058/8/22,�C1108/6/11,�D1112/9/22,�E1141/3/10,�F1148/4/20,�G1177/9/23�A���̓��t�͂قƂ�ǂ��t���O�ォ��H���O��܂ł̉Ă̊��ԂƂȂ��Ă���B����͉Ăɂ͑��z�̐Ԉ܂��������k�����̒��ܓx�œ��H����������m�����オ��ׂł���B
�P�D�Q �閾��̓��H�v�Z�@�ɂ�錟��
�@�閾��͒����ł�822�N892�N�܂Ŏg�p���ꂽ�B���{�ւ݊͟C�g����859�N�ɓ`�����A����܂ł̑埥��ɑ�����862�N����{�s���ꂽ�B���H�͌���0���ɑ��z�ƌ��������Ɣ����̌�_�߂��ɂ���ꍇ�ɋN���錻�ۂł��邪�A�閾��̓��H�v�Z�@2)�ł͌�������_����~��_�܂łɂ�����ԁi���̉��܂��������k�ɂ���ꍇ�j���A��ƌĂсA�t�̏ꍇ��z��ƌĂB����͌���̓��H�̃����v���X(=�A��)�̏ꍇ�ƃ}�C�i�X(=�z��)�̏ꍇ�ɂ��ꂼ��قڑΉ�����B�閾��ł͉A�z��̑��ɑѐH�i���H���̓��̏o�A���̓��j�A��H�i��̎��ԑтɓ��H���N����j�A�s�H�i�H�������œ��H�ƂȂ�Ȃ��j�̋�ʂ��v�Z���ʂƂ��ĎZ�o�����B�������閾��̂悤�ȌÑ�/�����̓��H�v�Z���@�ł͂��Ƃ����H���\������Ă�����̏ꏊ�ŋN���邩�ǂ����͊m��ł��Ȃ������B�����ł���Ɠ���������1001�N����1200�N�܂ł�200�N�Ԃ̓��H�����s�Ŋϑ��������̗���ȉ��Ɏ����B
�\�|�Q�@�閾��@�ł̋��s�ł̎����\��(����1001�N����1200�N)
|
���̈ʒu
|
���H�̎��
|
���H��
|
�����\(��-1)
|
�I����
|
|
�k�̏ꍇ(�A��)
|
�����H/�ѐH
|
91
|
65
|
71.4%
|
|
��H/�s�H
|
112
|
4
|
3.6%
|
|
��̏ꍇ(�z��)
|
�����H/�ѐH
|
101
|
10
|
9.9%
|
|
��H/�s�H
|
112
|
0
|
0%
|
|
���v
|
|
416
|
79
|
19.0%
|
�@�@��-1�F�����\�̌v�Z��Emapwin�ɂ��B
�@-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B
�@�\�|�Q�̌��ʂɂ���ʂ�A�閾��@�ł�����̓��H�v�Z�Ɠ����̊m��(69/79=87%)�Ō������z�̖k�ɂ���ꍇ�i�A��j�͓�ɂ���ꍇ�i�z��j��苞�s�Ō�����m�����������ƂɂȂ�B�܂����̕\���z��ƉA��̓����H�y�ёѐH��\�Ď����ł���m���͖�S��=(65+10)/(91+101)�ł��邪�A�A��Ɨz��̓��H�̔����m���𗘗p���ĉA��̓����H�y�ёѐH�݂̂�\��Ε��ϖ�V��=65/91�̗\�z�I�������邱�Ƃ��킩��B���ꂪ�z��@�ł���B
�Q�D���z�ƌ��Ƃ̑��Έʒu�ɂ����H�����m���̈Ⴂ�̔���
���H���ϑ��ł���m���́A���H�H�r���̌��̉��܂����z�̂�����k�ɂ���ꍇ�̕�����ɂ���ꍇ��舳�|�I�ɑ傫�����Ƃ��@�ɍŏ��ɍ̗p�����̂́A�@���ɂ��Ƒ�Ɨ�(�@�E��ƂS�N�AAD608�Ɏ{�s�B) ��Ҏ[�������h���Ƃ����B�@���@���h���B�ɂ���ނ̗�ƌ×��̗�Ƃ̈Ⴂ�̂R�ԖڂɁu�E�E�E�B�ጎ�s�����A���݉����V�k�A�H���L���B���s�O���A�݉����V���A嫋������A���R���f�A�H���s���B�����O�@�A�ʗ�����A�@�����߁A���C�����A���v�H���A���F�����B�v3)�@�Ƃ���A�����i�A��j�A�O���i�z��j�ɂ��v�Z�̕��@��ς����Ƃ���B���̂��Ƃ��M�����u�@����@�j�̌����v4)�Ɂu���̎O�͌��������̓숽�͖k�Ɉʂ���ɏ]�Ќ��̉������̌�_������x�����������Ƃ���͐H����͐H������̖@�𗧂Ă����Ƃł���v�ƏЉ�Ă���B�܂��@���E�u�̑�Ɨ�ɂ��u�E�E�E���]�@�]�������A�O������A�]�����H�A�ݓ����A��[�H]�B�v5)�Ƃ��肢�܂܂ł̗�@�ɂȂ��u�ݓ��ҁv�Ƃ������������Ă���B�܂����H������@���O���Ɠ����œ�ʂ莦���Ă���B
�Q�l�܂łɗ�㗥��u�ɍڂ���H���̋L�q�̕ϑJ�������B
�\�|�R�@�V������u�ɂ̂���H���̋L�q�̕ϑJ
|
��
|
�{�s�@�@(����)
|
�L�q
|
�L�ڌ�
|
|
�v���E�i����
|
237
|
���������ȏ�ҁA����A�]�����I�B
|
�u�b�ҘZ�@p.16966)
|
|
�v���E����
|
445
|
�������ȏ�A����A�]�����H�B
|
�u�b�ҘZ�@p.1730
|
|
�v���E�喾��
|
510
|
(������)�ȏ�A����A�]�����H�B
|
�u�b�ҘZ�@p.1752
|
|
鰏��E������
|
523
|
(������)�ȏ�A����A�]�����H�B
|
�u�b�ҘZ�@p.1791
|
|
鰏��E���a��
|
540
|
�����ݖ]�O�ҁA��������A�]�����H�B�����ݖ]��ҁE�E�E�B
|
�u�b�ҘZ�@p.1829
|
|
�@���E�J�c��
|
584
|
�ڍL�ږ����B
|
�u�b�ҘZ�@p.1893
|
|
�@���E���h����
(��Ɨ�)
|
597
|
�O������A�]�����H�A�ݓ����A��[�H]�B(��-1)
|
�u�b�ҘZ�@p.1925
|
|
�@���E�c�ɗ�
|
���{�s�i604�j
|
�����ȏ�Ҍ��H�A����[��]�����H�B
|
�u�b�ҘZ�@p.1957
|
|
�����E��Ќ���
|
619
|
��������A�]�����H�A�����ݓ������A���I�B
|
�u�b�Ҏ��@p.1986
|
|
�����E�ٓ���(�V�P��)
|
665
|
�ד��I���A�]�����H�A������A���ݗ����A���I�B
|
�u�b�Ҏ��@p.2024
|
|
�����E�埥��
|
728
|
�]���I���A�����H�A����I���A���݉A�������I�B
|
�u�b�Ҏ��@p.2024
|
��-1�F��Ɨ�̋L�ړ��e�B
��������z��̎����m�������Ȃ����Ƃ���������T�邽�߂��@���A�������̎j���ɍڂ���H�L����������H/�s�H�̓����\�|�S�ɂ܂Ƃ߂��B����ɂ����@�E�J�c�\�O�N(593�N8��)���Ō�ɂ���܂ŘA���I�ɗ\��Ă����z��̓��H�\��i�s�H�j���قƂ�ǖ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������B������@���E�u�̊J�c�\�l�N�V��(594�N)�ɋL�^�̂���Q�T�̉ߋ��̓��H�ɑ��錱�Z7)���W���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�Ȃ��Ȃ�A���̌��Z�̌��ʓ����{�s����Ă����J�c����h���̗�Ɋr�ח�邱�Ƃ��������R�N��̊J�c�\���N(597�N)��蒣�h���̗�{�s���ꂽ�̂ŁA���H�v�Z�ɂ��Ă͂��̎���茟���n�߂�ꂽ���߂Ǝv���邩��ł���B
�\�|�T�Ɋ���/�㊿���ɍڂ���H�L�^�̓�����܂Ƃ߂��������͔�H�������Ƃقڎ����̋L�^�ł���B���̋L�^���������ꍇ�A��̓��H�̊������������Ƃ͗e�Ղɔ��������Ǝv����B
�\�|�S�@�����̎j���Ɏc����H�L�^�̓���i���t�s��/�s�R�L���y�є�H�͊܂܂��B�j
|
|
|
�����\
|
|
��H/�s�H
|
�i��-2�j
|
|
|
�N��(����)
|
�S���H��
|
(��-1)
|
�A��
|
�z��
|
���v
|
�z�
|
|
550
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
100%
|
|
560
|
11
|
3
|
2
|
6
|
8
|
75%
|
|
570
|
9
|
4
|
2
|
3
|
5
|
60%
|
|
580
|
6
|
1
|
0
|
5
|
5
|
100%
|
|
590
|
3
|
0
|
1
|
2
(��-3)
|
3
|
67%
|
|
600
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
|
610
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0%
|
|
620
|
7
|
4
|
3
|
0
|
3
|
0%
|
|
630
|
8
|
3
|
2
|
3
|
5
|
60%
|
|
640
|
4
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0%
|
|
650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
|
660
|
5
|
2
|
3
|
0
|
3
|
0%
|
|
670
|
6
|
3
|
3
|
0
|
3
|
0%
|
|
680
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
|
690
|
5
|
4
|
1
|
0
|
1
|
0%
|
��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B
-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B
�@�@-3�F�Ō�̗z��̓��H��593�N8��
�@�@-4�F�u�����Ñ�̓V���L�^�̌��v8)�����Ƃɕ���
�\�|�T�@�����̌Îj���Ɏc����H�L�^�̓���i���t�s��/�s�R�L���͊܂܂��B�j
|
|
|
����
|
�s�I
|
|
|
|
�S��
|
�A��
|
�z��
|
���v
|
�A��
|
�z��
|
���v
|
��H
|
|
����
|
61
|
40
|
2
|
42
|
1
|
0
|
1
|
18
|
|
�㊿��
|
76
|
66
|
6
|
72
|
2
|
0
|
2
|
2
|
��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B
-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B
�@�@-3�F�u�����Ñ�̓V���L�^�̌��v�����Ƃɕ���
�@�Ȃ������ł͉A��z��͐閾��@�Ōv�Z���Ă��邪�A�ǂ̂悤�ȓ��H�v�Z���@�s�����Ƃ��Ă��A��y�їz��̓��H�̔����m���͂قړ����ł���A�܂��\�|�Q�Ŏ������悤�ɖk�܂R�T�x���x�̒n��Ŏ����ł���A��Ɨz��̓��H�̔䗦��9�F1�ł���B�]���ē��H�̌v�Z���ʂ����̂܂ܗp�����̂ł͕s�H�̊����͈��|�I�ɗz��̕��������Ȃ�B�Ⴆ�Ε\�|�Q�̏ꍇ�̕s�H�ł̗z��̊�����91/(26+91)=77%�ƂȂ�B�]���閾����ȑO�̓��H�v�Z���@�ł����Ă���قǐ��x�̈����v�Z���@�łȂ����蓯�l�̌��ʂƂȂ�B����Đ閾��Ōv�Z���ėz��̊������Ⴂ�ꍇ�͗z��̓��H�ɂ����삪�s��ꂽ�ƌ�����B
�R�D�z��@�̓��{�ւ̓`�d
�@���h���̕Ҏ[�����ŏ��̗�͊J�c�\���N(597�N)���{�s���ꂽ���A����̗�̔͂Ƃ��ꂽ�c�ɗ�i��Ǝl�N(AD608)�{�s���ꂸ�j��Ҏ[������焯�̎��㒣�h���͑O�̗�����ς������N����Ɨ�Ƃ��Ď{�s�����B��Ɨ�ɂ��c�ɗ�Ɋ�Â����ς��������悤�ł���B���̌��͓��ɂ����ĕ�Ќ���(�{�s�F619�N)�A�ٓ���i�{�s�F665�N�j�A�埥��i�{�s�F729�N�j�Ɖ��ǂ���čs�����B���̂Ȃ��ł܂��V�P����{�̋V�P�N�Ԃɓ`���A�����V�c4�N�i690�N�j����͋V�P��ƌĂꌳ�×�Ɣ��ɗp����ꂽ�B�埥����g���^�����V��7�N�i737�N�j�ɓ����玝���A��V����8�N�i764�N�j������3�N�i861�N�j�܂ŗp����ꂽ�B������864�N�܂ł̌܋I��p������o��865�N����͐閾��̎���ɓ���B
�@�����ł������Ɠ����l�ɗz��@���g���Ă��������m�F���邽�߂ɐ���1000�N�܂ł̋L�^���c����H�̂����s�H�̏ꍇ���A��Ɨz��ɕ��ނ������ʂ��\�|�U�ł���B���̌��ʂ���V�P��{�s���ꂽ��������z��̊����͒Ⴍ�z��@���g���Ă������Ƃ��m�F�ł���B���A�X���I�����i�埥��I�Ձj����P�O���I����(�閾��{�s��)�͑S�Ă̎�ނ̓��H�L�^���c���Ă���B����͊��ɂV���I�㔼����160�N�̗z��@��p�������H�\��̌o���������ł̂��Ƃł���A���H�v�Z���@�̖��Ƃ������A�v�Z���ʂ��������x���ς�������̂Ǝv����B9)
�@�\�|�T�̌��ʂ����ゲ�Ƃɂ܂Ƃ߂�ƈȉ��ł���B
�@689�N���F�����̋L�^�̂݁B
690�N��F���H�̐��Z�����߂����z��@�̎g�p�͂܂��m�肵�Ă��Ȃ��B
700-770�N��F�z��̊�����������z��@�œ��H�̐��Z�������Ȃ������Ƃ�������B
�@780-830�N��F��H/�s�H�̐�������قڎ����̋L�^�B
�@840-930�N��F�z��̊������オ��A�z�W�Ȃ��\���̌��ʂ��L�^�������Ƃ�������B
940-990�N��F�z��@�̓��H���Z�ɖ߂�B������970�N�ȍ~�͎����̂݁B
�@�܂��\�|�V��1000�N����1600�N�܂ł̓��H��O�Ɠ��������ނ������̂ł���B����ɂ��Ƃ��̊Ԃ��قڑS�Ă̊��Ԃɓn���ėz��@������ꂽ���Ƃ�������B1200�N�O��ɗz��̊����������Ă���̂͏h�j�����Ƃ̓��H�v�Z�Ɋւ��鑈���������ł���B
�\�|�U�@���{�̎j���Ɏc����H�L�^�̓���i����600�N�`1000�N/10�N���j
|
|
|
�����\
|
|
��H/�s�H
|
�i��-2�j
|
|
|
�N��(����)
|
�S���H��
|
(��-1)
|
�A��
|
�z��
|
���v
|
�z�
|
|
-689
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
|
690
|
8
|
1
|
3
|
4
|
7
|
57%
|
|
700
|
10
|
3
|
5
|
2
|
7
|
29%
|
|
710
|
11
|
2
|
7
|
2
|
9
|
22%
|
|
720
|
7
|
3
|
4
|
0
|
4
|
0%
|
|
730
|
10
|
3
|
7
|
0
|
7
|
0%
|
|
740
|
5
|
2
|
3
|
0
|
3
|
0%
|
|
750
|
4
|
0
|
4
|
0
|
4
|
0%
|
|
760
|
8
|
4
|
3
|
1
|
4
|
25%
|
|
770
|
9
|
2
|
7
|
0
|
7
|
0%
|
|
780
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
|
790
|
6
|
5
|
1
|
0
|
1
|
0%
|
|
800
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
|
810
|
7
|
4
|
3
|
0
|
3
|
0%
|
|
820
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
|
830
|
5
|
3
|
2
|
0
|
2
|
0%
|
|
840
|
8
|
4
|
2
|
2
|
4
|
50%
|
|
850
|
13
|
3
|
6
|
4
|
10
|
40%
|
|
860
|
14
|
5
|
3
|
6
|
9
|
67%
|
|
870
|
16
|
4
|
3
|
9
|
12
|
75%
|
|
880
|
16
|
1
|
7
|
8
|
15
|
53%
|
|
890
|
15
|
4
|
3
|
8
|
11
|
73%
|
|
900
|
13
|
3
|
4
|
6
|
10
|
60%
|
|
910
|
16
|
4
|
5
|
7
|
12
|
58%
|
|
920
|
7
|
5
|
0
|
2
|
2
|
100%
|
|
930
|
8
|
2
|
2
|
4
|
6
|
67%
|
|
940
|
9
|
4
|
4
|
1
|
5
|
20%
|
|
950
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0%
|
|
960
|
5
|
3
|
2
|
0
|
2
|
0%
|
|
970
|
5
|
4
|
1
|
0
|
1
|
0%
|
|
980
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
|
990
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B
-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B
-3�F�u���{�V���j���i��j�v10) �����Ƃɕ���
�\�|�V�@���{�̎j���Ɏc����H�L�^�̓���i����1000�N�`1599�N/50�N���j
|
|
|
�����\
|
|
��H/�s�H
|
�i��-2�j
|
|
|
�N��(����)
|
�S���H��
|
(��-1)
|
�A��
|
�z��
|
���v
|
�z�
|
|
1000
|
20
|
14
|
6
|
0
|
6
|
0%
|
|
1050
|
18
|
13
|
4
|
1
|
5
|
20%
|
|
1100
|
27
|
18
|
9
|
0
|
9
|
0%
|
|
1150
|
21
|
15
|
3
|
3
|
6
|
50%
|
|
1200
|
26
|
17
|
5
|
4
|
9
|
44%
|
|
1250
|
24
|
14
|
7
|
3
|
10
|
30%
|
|
1300
|
19
|
11
|
7
|
1
|
8
|
13%
|
|
1350
|
15
|
11
|
4
|
0
|
4
|
0%
|
|
1400
|
26
|
17
|
9
|
0
|
9
|
0%
|
|
1450
|
23
|
14
|
8
|
1
|
9
|
11%
|
|
1500
|
21
|
17
|
4
|
0
|
4
|
0%
|
|
1550
|
16
|
10
|
6
|
0
|
6
|
0%
|
��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B
-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B
�@ -3�F�u���{�V���j���i��j�v�����Ƃɕ���
�S�D���{�ł͂��z��@�͖Y���ꂽ��
�@�]�ˎ���ɓ�������L�v��1663�N�Ɂu���c�閾��Z�@�v���閾��@����ʂɎ�ɓ���悤�ɂȂ�������ɂ͗z��@�͖Y����Ă����悤�ł���B1670�N�Ɋ��������ї��R�Ȃǂɂ�芮�����ꂽ�u���{���ʊӁv�ɂ͒P�ƋL���Ƃ���1339�N����1600�N�ɂ����ėz��̓��H���������L�ڂ���Ă���B�u���{�V���j���v�̑O����18�j�ɂ��ƁA�����L�v�́u�{������v���t�Έ��́u�c�a�ʗ�I�l�v�͌��̌v�Z�ɂ����̂Ȃ̂ō̘^���Ȃ��Ƃ��邪�A�u���{���ʊӁv��1301�N�ȍ~�ɑ��̋L�^���������{�œ��H���������Ǝv������̂́u���{���ʊӁv���̘^���邱�Ƃɂ����Ƃ���B�������A�u���{���ʊӁv�ɒP�Ƃōڂ���H�͕\�|�W�ɂ܂Ƃ߂��悤�ɗz��̓��H���قƂ�ǂł���\�|�V�ł܂Ƃ߂����̓��H�L�^�̌X���Ƃ͑S���قȂ��Ă���B�]���āu���{���ʊӁv�ɍڂ���H�L�^�́u���c�閾��Z�@�v�Ⴕ���͑��́u�閾��@�v�����Ƃɂ������̓��H���Z�ɂ����̂ƍl������B�]���u���{���ʊӁv�̋L�����u���{�V���j���v���珜���ׂ����̂ł���B�u���{���ʊӁv�̋L�^�����p���Ă���u���j�����v�̋L�^�ɂ��������Ƃ�������B
�܂��ߔN�o�ł��ꂽ�u���{��������q���� �r�v11)�ɍڂ���H���X�g�ɂ��z��A��̋�ʂ��Ȃ��閾��@�Ő��Z�����s�H(�H������)�ȊO�̑S�Ă̓��H���L�ڂ��Ă���̂Œ��ӂ��K�v�ł���B
�\�|�W�@�u���{���ʊӁv12)�ɒP�Ƃōڂ����H�L�^�̓���
|
|
|
�����\
|
|
��H/�s�H
|
�i��-2�j
|
|
|
�N��(����)
|
�S���H��
|
(��-1)
|
�A��
|
�z��
|
���v
|
�z�
|
|
1339-1600
|
39
|
20
|
1
|
18
|
19
|
95%
|
��-1�F�����̌v�Z��Emapwin�ɂ��B
-2�F�A��z��̋�ʂ͐閾��@�̌��s���A�z��̌v�Z�@�ɂ��B
�@ -3�F�u���{�V���j���i��j�v�����Ƃɕ���
�T�D�܂Ƃ�
�@�@�����h���ɂ���ď��߂Ď{�s���ꂽ��@�֍̗p���ꂽ�z��@���V�P��Ƃ��ē��{�֓`���閾��g��ꂽ�]�ˏ����܂ŗp����ꂽ�B�z��@�̗̍p�ɂ����H�\��̎����m���͖�Q�{���P���A�Ⴆ�ΐ閾��ł͖�S���̎����m�����z��@���Ɩ�V���ƂȂ�B
(2008�N4��27��WEB�f�ځB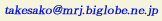 )
)
1) Jean Meeus Elements of Solar eclipses 1951-2200�vp8,1989, Willman Bell Inc.
2) �����L�v���u�čl���c�閾��Z�@�v(����}���ّ�)
3) �@���E�Z�@�B�@�����\��p1781,1973,���؏��Ǐo��
4) �M�����u�@����@�j�̌����vp18,1943,�O�ȓ�
5) �@���E��@�u�@���\��p.453,1973,���؏��Ǐo��
6) ���؏��ǕҏS���ҁu���V������u�b�ҁv(1975)
7) �@���E��@�u�@���\��p.429, 1973, ���؏��Ǐo��
8) �ē������E���u�����Ñ�̓V���L�^�̌��v,1992,�Y�R�t�o��
9) ��_�u���u�Ñ�V���ٕςƎj���vp112-117,2007,�g��O����
10) �_�c�Εҁu���{�V���j���i��j�v,������,1978,�����[
11) �Ð��i��Y,�ɓ��a�F,���c�F�N,��J���j���u���{��������q���� �r�v,�{�̗F��
12) �ї��R�u�{���ʊӁE���ҁv,1919,�������s��